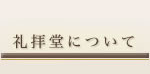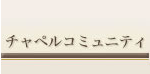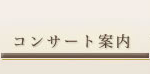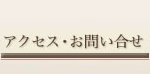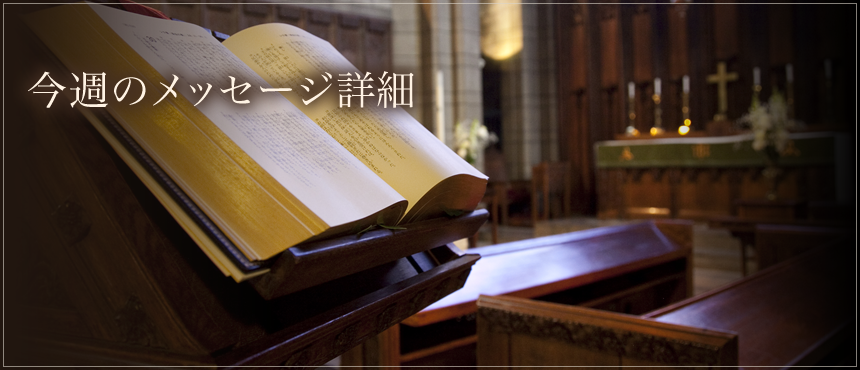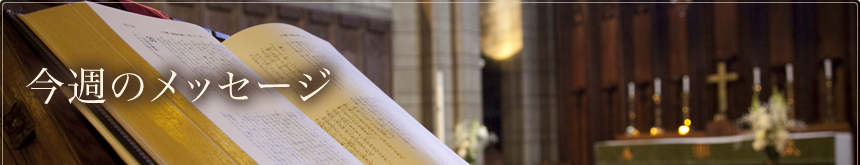チャプレン ヨナ 成成鍾 司祭
「 因果応報? 」
===
「言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。」
(ルカ13:5)
===
仏教から由来した因果応報という言葉があります。簡潔に言うと、原因があれば結果があり、その報いがもたらされるということを意味します。それで、良い行いは良い結果を悪い行いは悪い結果を生み出すとされるのですが、キリスト教にもそのような理解はあります。ところが大変残念なことに、自然災害や事故などの悲惨な出来事は神様の裁きであり、また悲劇に遭った人たちにはそれに相応の罪があったに違いないということを言う人もいます。今日の福音書によると、キリストの当時にもそのような人がいました。神殿で礼拝中に殺されたガリラヤ人たち、また塔が倒れて死んだ人たちは、実は罪深い人々だったので裁かれたのだという噂があったのです。それに対してキリストは、ずばりと「決してそうではない」(3節・5節)と否定されました。つまり、私たちの中にもある因果応報の考えに対して、それは神様のみ心ではないとはっきり語られたわけです。
それではなぜ世の中には頻繁に自然災害や戦争などの悲惨な出来事があり、何の罪もない人々に苦難や不幸なことが起こるのでしょうか。そしてなぜ全能の神様はそれらのことを許されるのでしょうか。その疑問を解決するためお祈りをしたり聖書や信仰書籍を読んだりするのですが、なかなか腑に落ちた答えは得られません。今日の福音書の中でもキリストはそれについては示されず、ただ「あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。」(3節)と語られただけです。一見これは答えにならないと思いがちです。ところが、このみ言葉こそそのような疑問を持つ私たちにとって何より大事な回答になります。なぜかというと、納得できる理由を見出すことが決して苦難や不幸の解決になることも、ましてや救いへと私たちを導くこともないからです。キリストは原因や理由ではなく、むしろその苦難や不幸の中で私たちが歩むべき道、つまり救いのために目指すべき方向とはどこなのかについて示されたわけですが、それこそ悔い改めということになります。
悔い改めということは、福音書を貫く核心になる概念の一つとして、人が救いへ導かれるための第一歩だと言えます。それゆえ、洗礼者ヨハネだけではなくキリストも「悔い改めよ、天の国は近づいた。」(マタイ4:17)と述べ伝えながら宣教活動を始められましたし、その後続く3年間の公生涯も人々を悔い改めさせて救いへ導くための活動だったと言えます。ここで言う悔い改めとは、生き方全体を変えること、180度方向転換することを意味します。いわゆるコペルニクス的転回(Copernican Revolution)のように、神様に背を向けていた私たちが向きを変えて神様の方向へと進んでいくということなのです。
では、今私たちにとって悔い改めはどのようなものになっているでしょうか。大斎節を過ごしている皆さん、悔い改めましょう。あなた一人の悔い改めが教会の悔い改めに、教会の悔い改めが社会の悔い改めに、社会の悔い改めが世界の悔い改めに展開していきます。放蕩息子が父の家に戻って行った(ルカ福音書15:11‐32)ように、私たちが神様に立ち帰ることができると、その影響が広がり、生態系破壊による自然災害は少なくなり、戦争などの悲惨な出来事もなくなっていくかもしれません。殆どの悲惨な出来事の原因は外ならぬ人間そのものにあるからです。
<福音書> ルカによる福音書 13章1~9節
1ちょうどそのとき、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜたことをイエスに告げた。 2イエスはお答えになった。「そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、ほかのどのガリラヤ人よりも罪深い者だったからだと思うのか。 3決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。 4また、シロアムの塔が倒れて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいたほかのどの人々よりも、罪深い者だったと思うのか。 5決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。」
「実のならないいちじくの木」のたとえ
6そして、イエスは次のたとえを話された。「ある人がぶどう園にいちじくの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。 7そこで、園丁に言った。『もう三年もの間、このいちじくの木に実を探しに来ているのに、見つけたためしがない。だから切り倒せ。なぜ、土地をふさがせておくのか。』 8園丁は答えた。『御主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥やしをやってみます。 9そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそれでもだめなら、切り倒してください。』」