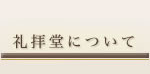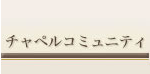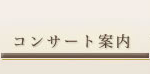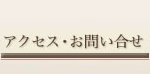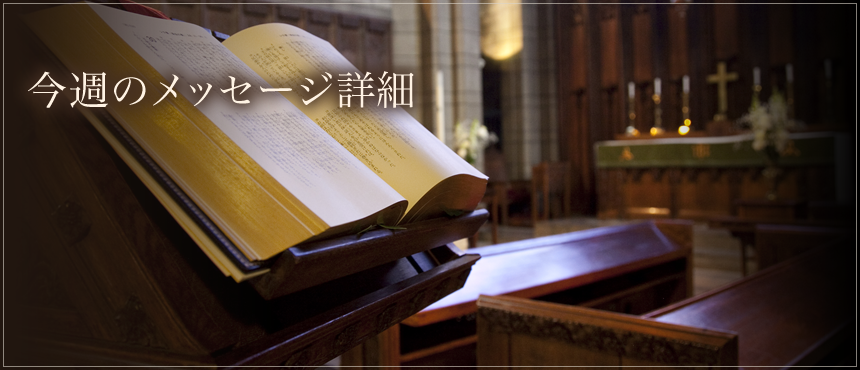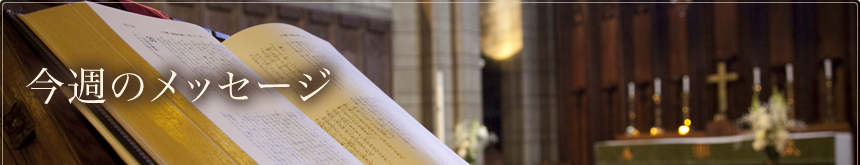チャプレン バルナバ 関 正勝 司祭
「 真理によって、彼らを聖なる者としてください。」 ヨハネ17:11c~19
聖なる父よ、
わたしに与えてくださった御名によって
彼らを守ってください。
わたしたちのように、
彼らも一つとなるためです。
わたしは彼らと一緒にいる間、
あなたが与えてくださった御名によって彼らを守りました。
わたしが保護したので、
滅びの子のほかは、だれも滅びませんでした。
聖書が実現するためです。
しかし、今、わたしはみもとに参ります。
世にいる間に、これらのことを語るのは、
わたしの喜びが彼らの内に満ちあふれるようになるためです。
わたしは彼らに御言葉を伝えましたが、
世は彼らを憎みました。
わたしが世に属していないように、
彼らも世に属していないからです。
わたしがお願いするのは、
彼らを世から取り去ることではなく、
悪い者から守ってくださることです。
わたしが世に属していないように、
彼らも世に属していないのです。
真理によって、彼らを聖なる者としてください。
あなたの御言葉は真理です。
わたしを世にお遣わしになったように、
わたしも彼らを世に遣わしました。
彼らのために、わたしは自分自身をささげます。
彼らも、真理によってささげられた者となるためです。
<メッセージ>
「真理によって、彼らを聖なる者としてください。あなたの御言葉は真理です」(17・17)
今日のヨハネ福音書に13章から16章まで記されている最期の晩餐の席でのイエスの決別の説教に続く、イエスの大祭司の祈りと言われる箇所であります。その祈りは御自分が世を去る時が今まさに迫っているその時に当たって、残される弟子たちのこと、そして教会のことに心を砕き祈っておられる箇所であります。「大祭司の祈り」と語られて来た「執り成しの祈り」と言われる部分であります。
13章に始まるその別れの説教ではイエスがご自分のことをキリストであることを弟子たちに明らかにされる時の特徴ある表現としてヨハネ福音書は「私は…である」(エゴ-・エイミ-)を用いて、多くを語られていることが示されています。例えば、14・06には「私は、道であり、真理であり、命である」と語り、15・01では「私は誠のぶどうの木である」と語ってご自分のことを弟子たちに明かしておられます。これらのイエスの自己啓示はご自分の時、すなわち十字架の死が直前に迫っているという緊迫感の漂う中での弟子たちへの別れのことば、励ましにほかなりません。ご自分に従って歩んで来た者たちをやがて襲うであろう不安や動揺を思ってイエスは語っておられます。しかし、イエスの彼らへの語りは安易な慰めの言葉ではありませんでした。むしろ厳しいイエス亡き後の彼らの信じる者としての歩みへの促しに他なりませんでした。
イエスは言われます。「私は、もはや世にはいません。彼らは世におりますが、わたしは御もとに参ります。聖なる父よ、私に与えて下さった御名によって彼らを守ってください。彼らも一つになるためです」(11)。ご自分が世を去り父なる神のもとに上ることを、さらにもう一度繰り返して語られます。(13)「しかし今、私は御もとに参ります。世にいる間に、これらのことを語るのは、私の喜びが彼らの内に満ち溢れるようになるためです」。そしてこの二つの言葉の間にイエスは彼ら弟子たちのことを思い「私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えて下さった御名によって彼らを守りました」と語られ、さらに「私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪い者から守ってくださることです」と祈られます。そして「真理によって、彼らを聖なる者としてください。あなたの言葉は真理です」(15、17)。ここに言われる「聖」とは道徳的にまた倫理的に清く正しい存在などを指す言葉ではなく旧約の預言者たちイザヤ(06・01以下)、エレミヤ(01・04以下)などの召命の出来事の中で語られているように彼らに使命が示される言葉に他なりません。
イエスは弟子たちに大きな使命・「世に遣わされる」という働きを託されています。真理の言葉によって聖なる者とされて「悪い者から守られて」、しかし「世から取り去られた者」として生きる生き方ではなく託された使命に生きる者とされることをイエスは父に祈っておられます。この緊張関係、すなわち神によって生かされる「この世の者ではない・超俗性」と同時に「この世性」を生きるという、イエスに従う者の生き方がここで語られていると言えましょう。彼らは「世から出た者ではない」神によって新しく誕生したものたちである。それゆえに世は彼らを憎み、迫害し、追い出そうともするに違いない。しかしそのことのゆえにこの世界からまた社会の現実から逃避したり超越して軽蔑したりすべきではない。イエスは言われます。「私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪い者から守ってくださることです」。何と私たちにとっても大きな挑戦的な言葉であることでしょうか。信仰はこの世性を否定したり、また超越して生きることでもない。そして、また逆にこの世にどっぷりとつかりきって埋没してしまうことでもない。「聖」ということが預言者たちに求められた使命に生きる召命を意味するように、弟子とされた者たちにとって(あるいは友と呼ばれる者にはなおさらのこと)「超越と内在」の緊張関係を生ききることが求められている、ということであります。何と大きな緊張であることでしょうか。
この困難な課題をユダヤの宗教思想家は高い山で、足をどちらかに引きずり落とされがちな「狭い尾根」を歩むことに譬えました。それはヒットラ-の国家社会主義に抵抗したドイツの牧師にして神学者のD・ボンヘッファ-が「この世性」とは「徹底的な訓練を経た深いこの世性であり、また、そこで死と復活とが常に現在的であるところの深いこの世性」と語ったことに通じておりましょう(『抵抗と信従』)。この彼の言葉はわたしたちにこの世界、この社会の中でキリストに従って生きる、生き抜くことで初めて信じることを学ぶことを指さしているのではないでしょうか。
作家遠藤周作の小説『沈黙』でも踏み絵を前にしたロドリゴらキリシタンの決断も彼らは転んだのではなく、むしろ「匿名のキリスト者」として生き抜くことを選んだ人々ではなかったのではないでしょうか?「深い訓練されたこの世性」を生きる道を選んだ、と申したら言い過ぎでしょうか?
いずれにせよ、十字架の死を直前にしてイエスは弟子たちに「世から出た者ではない」しかし「世から彼らを取り去る」ことをは願われず、彼らを「聖」として召し出し、彼らを「世に遣わされました」。確かにこの世は私たちにとってしばしば「死の陰の谷」(詩編:23・04)の歩みの如く、困難に満ち、苦しく、生き難い世であります。しかし、私たちのその歩みにはイエスの「私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪い者から守って下さることです」との祈りが支えて下さっていることを堅く信じる者でありたい。「真理」である父なる神の「言葉」が、私たちの行く手を導き、支えて下さっていることを信じてこの「狭い尾根」を共に歩んでまいりたいものです。 ア-メン