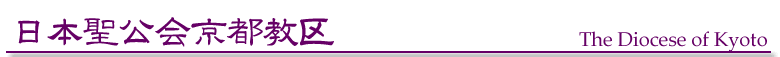 |
||||||
|
2024年5月5日 復活節第6主日(B年) |
司祭 ヨハネ 黒田 裕 応答としての愛【ヨハ15:9-17】 わたしは若い頃「愛」という言葉があまり好きではありませんでした。例えばⅠコリ13:4-7(愛の賛歌)などは、この通りにできなくては愛と呼べないのなら自分には無理だ、としか思えなかったからです。しかし後年このような受け止め方をするのは、こうした箇所を律法的に読んでいたためではないかと気づきました。これらは律法というよりも神さまによってなされた現実ではなかったでしょうか。実際この「愛」一つひとつに「イエス」という言葉を当てはめても成り立ちます。そして現にヨハ15:12では、あくまでも、「互いに愛し合いなさい」の前に「わたしが…愛した“ように”」が来ています。ひとが誰かを愛する前に、イエスさまが人間を愛したのです。 しかし、その一方でイエスさまの「愛」の大部分は誤解や拒否に遭っています。民衆の中であれだけ多くの病者を癒し、様々な奇跡をおこされたにも関わらず、結局裁判の時には、群集によって「十字架にかけろ!」と言われてしまうのです。また、イエスさまについていくことを誓った弟子たちも十字架の時には裏切ってしまいます。しかしそれでもなお、イエスさまは神さまのみ心に委ねて十字架への道を進まれました。それがイエスさまの「愛する」でした。聖書では神さまの愛をアガペー=無条件の愛と表わします。が、それは決して、あらゆる面で超越的な神であるがゆえに無傷で痛みなくなされたというわけではありません。無条件に愛そうとするからこそ必然的に痛みを伴います。痛み苦しみを伴いつつ、思い通りにゆかないことも引き受ける愛だったのです。そのような愛はこの世的にはまことに無力で、そのため十字架上の死によって一旦は無に帰したかに見えます。しかし、そのような愛はまた神さまにしかできない業であるがゆえに、ご復活というかたちで貫徹されたのでした。そのことに思い至るときに必然的に感謝の念が湧き起こります。そして、その流れのなかに、「互いに愛し合う」(15:12)の「愛」があるのではないでしょうか。 それは、「ねばならない」という律法ではありませんし、強迫観念に基づく愛ではなく、自己に根拠を置いた独りよがりの愛でもありません。神さまへの応答としての愛です。応答としての愛ならわたしたちにもできるかもしれない、神さまがわたしたちを愛してくださったということに応える愛である、ということを今日皆で分かちあいたいと思います。
|