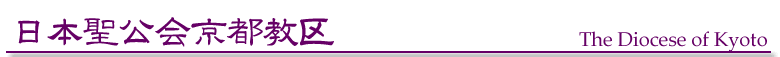司祭 セシリア 大岡左代子
「父は、憐れに思い・・・」
ルカによる福音書の第15章は、よく「無くしたものシリーズ」と言われます。新共同訳聖書の小見出しには、「見失った羊」のたとえ、「なくした銀貨」のたとえ、「放蕩息子」のたとえ、と記されています。フランシスコ会聖書研究所の聖書には、15章の始めに「憐れみの三つの喩えの序」とあり、本田哲郎神父訳の聖書には「一匹の羊」「一枚の銀貨」「一人の息子」と「いち」に焦点が当てられています。
この聖書箇所を高校生と読んだ時、「わたしはこのお話は大嫌い!不公平や!」という声を聞きました。教会で読んでも、同様の思いを聞くことがあります。多くの人は兄に同情をし、自分を重ねます。そもそも父の財産の生前贈与を受けること自体が、当時は大変非常識な要求でした。その弟の願いをかなえたことは兄にとっては不愉快極まりない出来事だったでしょう。その非常識な弟が戻って来たうえに、父が法外な喜びをもって迎えたのですから面白いはずはない、と思うのはわたしたち人間の通常の感覚かもしれません。けれども、わたしたちにはこのような感覚、思いがあるからこそ、イエスさまはこの喩え話を語られたのではないか、とも思うのです。
わたしはこの「無くしたものシリーズ」の聖書箇所を読むと思い出す出来事があります。わたしの息子が3歳になる前に行方不明になった出来事です。兄たちに留守番を頼んで1時間ほど外出をしている間のことでした。帰宅したら行方不明になっていて、家族や知人で必死になって捜しました。わたしは生きた心地がしませんでした。何度も何度も留守番させたことを悔い、最悪の事態を想像しました。そして2時間くらい捜した結果、彼は大人の足で7〜8分のところにある大型スーパーにいることがわかりました。「いました〜!」との電話をうけ、そのスーパーへ走っていき、子どもの姿を見つけたとき「ここにいてくれてよかった。無事でよかった。」と、ただただ子どもを抱きしめていました。子どもは、もしかしたら「叱られるのではないか?」とドキドキしていたかもしれません。けれども、ただ<この子がいてくれてよかった。>という思いしかわたしの中にはなく、彼を見つけた喜びと感謝しかありませんでした。
「まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した」20節に記されているこの父親の行動の発露は、息子を見つけて「憐れに思った」ことです。「憐れに思う」それは「はらわたが突き動かされるような思いになる」ことです。
居ても立っても居られない、心がうずいて行動を起こさずには居られない、ここに神様の愛があるのです。わたしたちは、神様の目から見ればいつも大切な「いち」です。いつも一人ひとりを捜してくださっています。放蕩の限りを尽くした弟が「われに返った」ように、わたしたちも自分自身を知るとき、より深くその神様の愛に気づくことができるのではないでしょうか。この後、兄もきっと深い父の愛を知ったのではないかと思います。
|