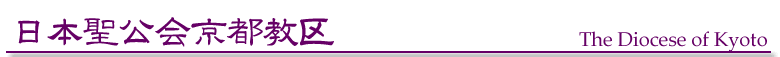執事 プリスカ 中尾貢三子
「神が結び合わせたものを、人は離してはならない。」
【マルコによる福音書10章2節−9節】
「神が結び合わせたものを、人は離してはならない。」
この言葉が語られたのは、次のような場面でした。登場人物は、ファリサイ派の人々と、イエスさま。ファリサイ派の人々は、神様の教えをきちんと、立派に守っている、正しい生活をしているという自負がありました。一方、イエスさまは、のびのびと、出会った人一人ひとりとの生き生きとした交流を通して、相手のいのちに生きる力を取り戻させ、病を癒しておられました。その姿は、ファリサイ派の人々からみれば、あまりにも自由すぎる、許せないと思うことが多かったのでしょう。彼らは、何度もイエスさまに人々の前で議論をしかけました。
「夫が妻を離縁することは、律法にかなっているでしょうか。」
イエスさまは、ファリサイ派の人々に、天地創造の物語を思い出させました。
神様によって造られた人(人、人類、男性、固有の人名「アダム」)は、自分のあばら骨から造られた人(イシャー)を見て
「ついにこれこそ、わたしの骨の骨、わたしの肉の肉。
これをこそイシャー(女性、妻)と呼ぼう。まさにイシュ(男性、夫)から取られたものだから」
言葉遊びのように見えるかもしれませんが、イシュという単語の冒頭と末尾の文字からつづった単語がイシャーなのです。それほど不可分に結びついたパートナーとして、彼女の存在を喜んだのではなかったか、と言われるのです。分ちがたく結びついている関係を、モーセが人間の心のかたくなさを見て書いたものによって離してしまってよいものかどうか、考えるように促されました。それが「神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない」という言葉でした。
離縁状ひとつで女性たちを離縁することの可否だけを問題にしたファリサイ派の人々に向かって、具体的な窮状を知っているからこそ発せられたイエスさまのこの言葉は、この状況の元での警告であったはずです。それが、この文脈から切り離されて「一人歩き」してしまう危さを感じています。
いのちや喜びが行きかうような関係どころか、自分の存在の根底やいのちでさえ脅かされかねない状況にある女性たち、男性たちに向かって、この言葉を引用して「結婚」という制度の中に留まることを勧める(強いる?)ことは、律法の規程どおりだからということで離縁を「合法化」した人々と変わらないのではないでしょうか。
イエスさまの、人を生かすいのちの言葉。それを誰かを押さえつける言葉として用いていないだろうか。言葉が発せられた状況を抜きにして、イエスさまの言葉を用いるとき、人のいのち、生きる力を奪うほどの「暴力」になりかねないのだということを、自戒を込めて心に刻みたいと思います。