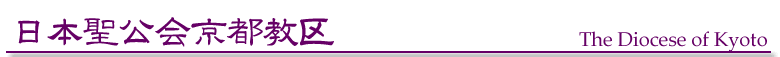司祭 バルナバ 小林 聡
罪を問われる姿【サムエル記下11:26−12:10、13−15】
罪を問われるということがどういうことなのか、私たちはダビデという人物の告白を通して、思い巡らしてみたいと思うのです。罪を認めるという時、そこには一種の葛藤が生まれます。昔私は小学生の時、壁にボールを当てて遊んでおりました。ある瞬間ボールは壁の上の方の穴を通り抜けて隣の家に飛び込んでいきました。ガチャーーンと言う音とともに、私は即座に逃げる態勢をとっておりました。その敷地内から出て行く瞬間、思いもよらぬ場面に遭遇したのでした。なんとその家のおばちゃんが買い物から帰ってきたのです。私は思わず、ごめんなさいと謝りました。反射的に、ここは謝っておいた方が後々徳になると、計算したのでした。案の定、そのおばさんは、割ったのに素直に謝るいい子と言ってくれたのでした。もちろん親にも伝わりますので、謝った方が良かったとつくづく思うのでした。ただ、もしあそこでおばちゃんに遭遇していなければ確実にとんずらしていただろうと思うのです。
私がこのことから学んだことは、謝った方がその後の人間関係がうまくいくということ以上に、人は謝ることをも計算に入れる生き物なのかと、自分の罪深さに驚いたことなのでした。
罪というのは、神に向かう方向から反れることをいいます。反れるとどうなるかというと、色々人に迷惑をかけたり、それに気づかなかったり、悪いことを引き起こしたりします。もっと言えば自分の本性に向き合うことを避けてしまいます。だからまず神様の方を向いているのかどうか、それに気がつかないといけないわけです。
ところが、立場が違ってくると、罪が見えなくなる危険があります。今日の聖書の箇所のように王たる者が、罪を認めて、それを告白するというのは、世の常ではなかなかないことですね。それを覆い隠せてしまう立場の人は罪を犯していても気がつかないか、罪を告白する必要がありません。ところが聖書は人間の弱さ罪深さを抉り出すような物語が描かれています。
ダビデ王の犯した罪は、イスラエルの歴史の中でも隠しておきたい部分であっただろうと思います。しかし、聖書はダビデの罪深さをこそ読者に伝えようとしているように思えるのです。ダビデは人々の上に立つ指導者でありながら、戦いに出ず、宮廷にいました。そのことはダビデが家臣の気持ちを裏切り、自分の立場に安住している姿をあらわしているのです。王たる者は、知らず知らずに自分がしてしまっている堕落の姿が見えなくなるものです。そして家臣の妻を我が物にし、その夫を激戦地に送り込み、忠実な家臣を殺してしまいました。その後、その家臣の妻を自分の妻としました。自分には何でも出来ると思ったのでしょうか。ここに人間の愚かさ、弱さが露呈しているのです。
そこで主に遣わされたナタンがダビデを叱責します。ナタンは王に苦言を呈する役割を担いますがそれは命がけでした。ここでダビデの告白があります。「わたしは主に罪を犯した。」と。ナタンとのやり取りは、ダビデを罪の告白へと導きました。私たちはここで、ダビデのした告白に大きな信仰的謙虚さを見て取るはずです。しかし私は、このダビデの罪の告白を、ダビデの謙虚さという話で終わるものではなく、人間の本性を問い続けるために、罪の姿をさらけ出すという、聖書の編集者たちの信仰的姿勢と捉えたいのです。
私の小学生時代の告白ではありませんが、人間が行なう罪の告白はそれ自体が絶対的価値を持つものではなく、人間の持つ自己中心的な本性に向き合えることこそが聖書が伝えようとしてきたことではないかと思うのです。傷つけてしまったすべての人の視点、つまり神さまの視点を通して、自己完結したいと思う弱い自分を問い続ける姿勢こそが、心からの悔い改めなのです。苦しいけれども、問われる姿を曝し、犯した過ちに向き合い続ける姿が信仰的姿勢であることを聖書は伝え続けてきたのです。