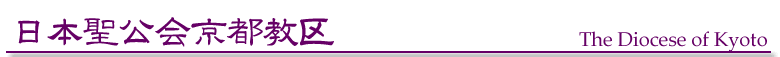司祭 ヨハネ 黒田 裕
神さまの“親心”
言は肉となった―これは、神の子は人間の姿でこの世に来られた、救い主イエス・キリストは肉体をもってこの世に来られた、という福音の奥義ですが、最近、これを身近な例で譬えた話しを聞く機会がありまして、目からウロコが落ちるような思いがいたしました。あるベテランの牧師さんなのですが、彼は、神さまがイエスさまをこの世に遣わしたというのは、独り暮らしをする息子のところに親が直接訪ねていくようなものだ、というのです。
どういうことかというと、独り暮らしをする息子は、たまに経済的にピンチになると、親に仕送りをお願いする。昔でいえば電報で「カネオクレ」とでも打つところでしょうか。すると、ほどなく親から現金封筒が届く。ということが日常なのですが、ある日突然、心配になった親が、息子の下宿に訪ねてくる―このことに似ているというのです。
ここで彼の鋭い指摘があるのですが、それは、息子の気持ちをクローズアップするのです。突然親に訪ねてこられた息子の気持ちはどうか。「ああ、よく来てくれました、お父さん(お母さん?)」、というのはたいへん優等生な子供です。しかし普通はどうでしょうか。「とても迷惑な気持ちになるのではないか」、というのです。これは、とても良く分かります。自分だったらどうかと考えてみても―今となっては大変親には申し訳ないことなのですが―やはり「やめてくれ」「こないでくれ」という気分になったに違いありません。息子にとっては、現金書留だけ送ってくれればそれで良いわけです。勝手気ままにやっているところに、突然来てほしくない。要るもんだけもらえたらそれでいい。
しかし、ひるがえって、親の気持ちはどうでしょうか。親は常に子のことを思っていろいろ心配しているはずです。元気でやっているか、失敗してないか、落ち込んでいないか、最近冷え込んできたけど寒くないか、風邪ひいてないか…。そしてお金を送るときでも、これはただのモノの移動ではなくて、これ自体に思いがこもっているはずです。現金封筒はイスラエルにあてはめていえば、ちょうど律法のようなものといえるかもしれません。律法は目に見える形では文字ですが、これ自体に神さまの子を思う気持ちが表されています。最初に送られた現金書留、いや律法は、十戒でした。ざっとふりかえってみますと、
①あなたはわたしのほかに、何ものをも神としてはならない
②あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。
(中略)それにひれ伏してはならない。
③あなたは、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。
④あなたは、安息日を覚えて、これを聖とせよ
⑤あなたの父と母を敬え
⑥あなたは殺してはならない
⑦あなたは姦淫してはならない
⑧あなたは盗んではならない
⑨あなたは偽証してはならない
⑩あなたはむさぼってはならない
このどれをとっても子を思う親の気持ちがあらわれています。どれがないがしろにされてもイスラエル=わが子は、ダメになってしまう。都会、じゃなくて荒れ野はさまざまな誘惑に満ちていました。自分の親を忘れて別の「親分」についてゆく誘惑。欲望におぼれてしまって放縦にふける誘惑。また、荒れ野の厳しい生活のなかでは基本的な倫理を守っていかなければ、イスラエルはバラバラになってしまう危険性が大いにありました。(第5戒の)父と母とは、当時としては老人で、幼い子供と共に共同体のなかでもっとも弱い存在でした。危機が訪れると真っ先に犠牲になるのがこれらの人でした。これらの人たちが大切にされないと早晩イスラエルは、内部崩壊を免れませんでした。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、むさぼるな、これらの最低限の戒めをとってもみても、これが守られなければ共同体の維持は不可能でした。
このように、これらの戒めはどれをとっても、これが守られなければ、イスラエルがイスラエルでなくなる、息子が息子がでなくなる、というような事柄でした。神さまは、我が子が誤った道にそれていかぬように、人間らしい豊かさをもって成長していけるように、そうした親心を込めて、こうした律法を人間に与えたのでした。
ところが、これを守れないのも人間の現実でありました。私自身、ふりかえると親のしてくれたことや送ってくれたお金をずい分無駄に使ってしまったと今では思います。とんだ愚息です。心配になった親は、そこでどうするか。とりあえず現地にいるか、近くに住んでいる自分の知り合いに、「ちょっと息子がどうしてるか見てきてくれないか」と頼みます。預言者が送られたのは、これに似ているのではないでしょうか。しかし、預言者の努力も空しく親の心配は取り去ることができないでいました。
そして、ついに親は決断するのです。こうなったら自分で行ってこよう。こうしてイエスさまがこの世に来られたのでした。もはや事態は、現金書留や知人では済まないところまで来ていたのです。神さまの心配は頂点に達し、その胸は張り裂けそうでした。そしてやむにやまれず人間の形をとって神さまみずからが来られたのでした。
そんな親の気持ちも知らず私たちは「迷惑」に思ってしまう。当時のイスラエルがそうでした。邪魔で邪魔でしかたなかったのです。親の心、子知らず、とはまさにこのことです。あるいは、“親孝行したいときには親”はなし。親の心を知ったときには、すでにイエスさまは十字架につけられ、天に昇った後でありました。
しかし、「放蕩息子」のたとえのように、どんな愚息も、父の家に帰ろうとすれば必ず受け入れてもらえます。それどころか、まだ遠く離れていたのに息子を見つけた父は、父自らかけよってきて息子を抱き接吻までしたのでした。
言は肉となった―この、文字にすればわずかな数の短い文のなかに、神さまの計り知れない親心が込められています。私たちはそのことを深く心に感じ、感謝と賛美をささげて、この一年をしめくくることとしたいと思います。